Lenovo製品に関しては、「やめとけ」「買ってはいけない」といった否定的な声がネット上で目立ちます。
「レノボジャパンはやばいのでは?」という意見や、過去の不祥事をめぐる議論も見受けられます。
こうした評判や噂の中には、実際の事例に基づいたものもあれば、誤解や古い情報が一人歩きしているケースもあります。
特にセキュリティ問題やサポート体制への懸念、製品の品質に関する不安など、「危険」とされる要素が複合的に語られているのが現状です。
本記事では、Lenovoがどこの国のメーカーなのかという基本情報から始まり、「やめとけ」と言われる根拠や実際の評判、さらには日本法人であるレノボジャパンの実態まで、幅広く解説します。
事実と憶測を切り分け、納得できる選択ができるようサポートする内容となっています。
Lenovoはどこの国のメーカー?やめとけと言われる理由とは
- Lenovoはどこのメーカーなのか徹底解説
- レノボが中国製と敬遠される理由
- やめとけと言われる背景にある問題
- 買ってはいけないと言われる3つの根拠
- レノボジャパンはやばい?その実態
Lenovoはどこのメーカーなのか徹底解説

Lenovo(レノボ)は、中国発祥のグローバル企業であり、パソコンやタブレット、スマートフォンなどの情報機器を製造・販売しているITメーカーです。
1984年に中国科学院計算技術研究所の支援を受けて設立された「Legend(レジェンド)」が母体で、2004年に「Lenovo(新しい伝説)」という社名に改められました。
世界的に知られるようになった大きなきっかけは、2005年に米国IBMのパソコン部門を買収したことです。
これにより、当時高い信頼性を持っていたThinkPadなどのブランドを継承し、ビジネス向けPC市場で大きな存在感を示すようになりました。
現在では、HPやDELLと並び、世界のPC出荷台数ランキングで常に上位に名を連ねています。
日本においては「レノボ・ジャパン合同会社」という日本法人が存在しており、東京都千代田区の秋葉原に本拠を構えています。
また、日本企業であるNECや富士通のPC部門とも提携・統合しており、一部製品は日本国内で開発・製造されています。
たとえば、NEC米沢事業所ではThinkPadの一部モデルが「米沢生産モデル」として製造されています。
つまり、レノボは中国企業である一方、アメリカや日本との強い連携のもとでグローバルに展開しているメーカーです。
中国本社に加えて、日本やアメリカに研究開発拠点を持つなど、複数の国と技術・生産の連携を行っているのが特徴です。
このように、多国籍の技術とノウハウが集まっている企業であるため、単純に「中国のメーカーだから不安」と考えるのは、やや一面的だといえるでしょう。
レノボが中国製と敬遠される理由
レノボが敬遠される理由の一つに、「中国製品」に対する消費者の警戒心があることは否定できません。
近年の国際情勢や報道の影響により、中国製品に対して「セキュリティが不安」「情報が抜かれるのではないか」といった懸念を持つ人が増えています。
これはレノボに限らず、ファーウェイやZTEといった他の中国メーカーに対しても見られる傾向です。
実際、レノボは過去に「Superfish事件」と呼ばれる不祥事を経験しています。
これは2014年~2015年に出荷された家庭用PCに、ユーザーの通信を解析する広告ソフト(アドウェア)が意図せずプリインストールされていたという問題で、セキュリティリスクが指摘されました。
この出来事が「中国製のPCは危険」というイメージを強める一因になったと考えられます。
また、中国には「国家情報法」という法律が存在します。
これは中国の企業や個人が国家の情報活動に協力しなければならないという内容を含むものであり、これにより「政府が企業を通じて情報を収集するのではないか」という不信感が海外でも生まれています。
一方で、レノボは日本やアメリカでも研究開発を行っており、製品の一部は日本国内で製造されています。
すべてが中国国内で設計・生産されているわけではない点も理解する必要があります。
たとえば、NECと共同で開発されたモデルでは、日本独自の品質管理や設計思想が取り入れられています。
このような背景から、レノボ製品が「中国製だから避けたい」と見られることもある一方、実際には国際的な共同開発や日本国内での製造も行われており、すべてのレノボ製品を一括りに危険とするのは早計と言えるでしょう。
やめとけと言われる背景にある問題

「レノボはやめとけ」と言われる背景には、いくつかの誤解や過去の出来事が複雑に絡んでいます。
単に性能や価格だけではなく、サポート体制や企業イメージ、セキュリティ問題などが購入判断に影響を与えているのです。
まず、先述のSuperfish事件は、多くのユーザーに不安を与えました。
この件でレノボは信頼を大きく損ない、一部では「バックドアが仕込まれていたのではないか」という疑念が広まりました。
現在は解決済みで再発防止策も講じられていますが、ネット上では依然としてこの話題が尾を引いています。
さらに、サポートに関する不満の声も目立ちます。
レノボはグローバル企業であるがゆえに、日本独自の「きめ細やかなサポート」を期待していたユーザーからは、「対応が遅い」「問い合わせが複雑」といった感想が出ています。
特に初心者や高齢のユーザーにとっては、国内メーカーのサポートと比べると不満を感じやすいかもしれません。
加えて、「中国製品全般に対する不信感」も見逃せません。
前述の通り、国家情報法の存在や国際情勢に影響を受け、「レノボ=危険」「やめとけ」と語られることが多いのが現状です。
たとえ実害が確認されていなくても、リスクを回避したいという心理がそのような評判を後押ししています。
一方で、レノボは世界トップクラスのPC出荷数を誇り、企業や自治体、教育機関にも多く導入されています。
ビジネス向けのThinkPadシリーズなどは特に評価が高く、信頼性も確立されています。
このように「やめとけ」と言われる背景には、過去の事件・セキュリティ懸念・サポート体制の不満などが複合的に関わっています。
購入を検討する際は、これらの点を踏まえたうえで、自分の利用目的や重視したいポイントに合致するかどうかを冷静に判断することが大切です。
買ってはいけないと言われる3つの根拠
レノボ製品が「買ってはいけない」と言われる背景には、主に3つの明確な懸念点があります。
それぞれの要素が、ユーザーの不安や不信感につながっているといえるでしょう。
まず1つ目は、セキュリティ面への不安です。
レノボは過去にアドウェア「Superfish」がプリインストールされた製品を販売していたという問題がありました。
この件により、ユーザーの個人情報が外部に漏れる可能性があったとされ、大きな批判を浴びました。
こうした過去の事例は、たとえ現在改善されていても、購入前の判断材料として強く意識されてしまいます。
2つ目の理由は、サポート体制やアフターサービスに対する不満の声です。
レノボはグローバル企業であり、日本国内でもサポート窓口がありますが、「対応に時間がかかる」「説明が不十分」「言葉が通じにくい」といった利用者の声が一部で見受けられます。
とくにパソコンに不慣れな人にとっては、サポートの質は非常に重要です。
国内メーカーに比べてこの点で不安を感じる人が多く、「初心者には向かない」と評される原因にもなっています。
そして3つ目は、中国メーカーであることに対する懸念です。
これは技術や性能とは関係ない話ではありますが、昨今の国際情勢を背景に、中国企業への不信感を持つ人が増えています。
中国政府と企業の関係性や、法律による情報提供義務などが話題となる中で、「情報が抜き取られるのでは?」という漠然とした不安が先行しやすい状況です。
これら3つの根拠は、事実に基づいたものもあれば、誤解や過去のイメージによる部分もあります。
ただ、どの理由も購入検討者にとっては無視できないポイントであり、それぞれの懸念に対して自分がどう感じるかを判断することが大切です。
レノボジャパンはやばい?その実態
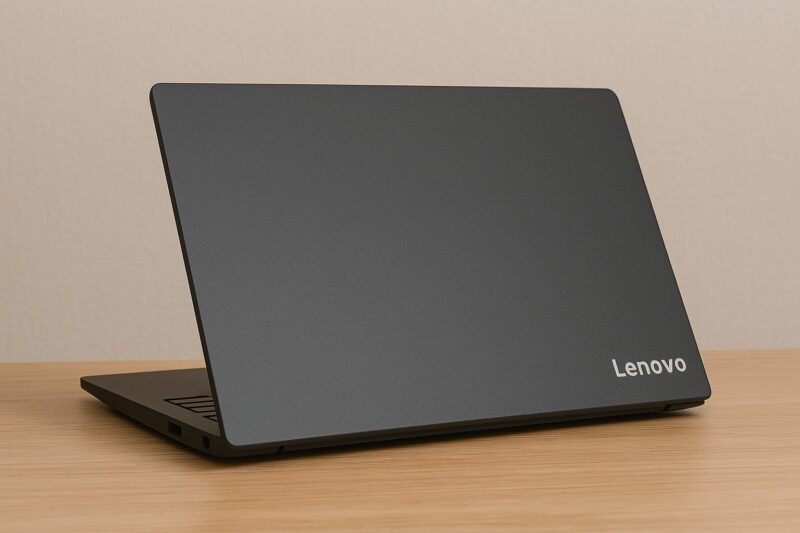
「レノボジャパンはやばい」という声をネット上で見かけることがありますが、実態を冷静に見ていくと、必ずしも極端にネガティブな評価ばかりではありません。
このような表現の背景には、一部ユーザーの不満や誤解、そして情報の断片的な受け取り方が関係していると考えられます。
まず、「やばい」と言われる理由の一つはサポートの質に対する評価のばらつきです。
レノボジャパンは日本国内におけるレノボ製品のサポートと販売を担う企業ですが、サポート対応が「遅い」「問い合わせがつながらない」「内容が伝わりにくい」といった声があることも事実です。
ただし、これはサポート体制の改善途上にある企業ではよく見られる課題でもあります。
次に挙げられるのは、製品の品質に関する意見のばらつきです。
レノボジャパンが扱うPCは、低価格帯からハイスペックモデルまで幅広く、価格に応じて使用パーツや組み立て場所が異なります。
特にエントリーモデルでは、「キーボードが打ちづらい」「ディスプレイの視野角が狭い」といったレビューが目立ちやすくなります。
一方で、法人向けやビジネス用途のThinkPadシリーズは堅牢性・信頼性に定評があり、多くの企業や教育機関でも採用されています。
また、誤解されがちですが、レノボジャパンは完全な中国企業ではなく、NECとの合弁会社としての側面も持ちます。
一部の製品は日本国内で設計・開発・生産されており、品質管理も日本基準で行われています。
これにより、一定水準の品質と信頼性を保っている製品も多く存在しています。
このように、「レノボジャパンはやばい」という声には、根拠のあるものもあれば、単なる不満の表現や一部情報に偏った評価も含まれています。
購入を検討する際は、実際の使用目的や必要な性能、サポート体制を確認し、自分に合った製品かどうかを判断するのが適切です。
Lenovoはどこの国のメーカー?やめとけは本当か検証
- Lenovoに危険性はあるのか?
- 過去の不祥事とセキュリティ問題
- レノボの評判は実際どうなのか
- レノボのサポート体制と国内生産事情
- やめとけと騒がれる理由は都市伝説?
- レノボを選ぶべきユーザーの特徴とは
Lenovoに危険性はあるのか?

Lenovo製品に対して「危険性があるのではないか」と不安を抱く人は少なくありません。
こうした印象は、過去のセキュリティ問題や製品トラブル、そして国際的な政治的背景によって形成されたものです。
とはいえ、現在のLenovoが本当に危険な製品を提供しているかどうかは、慎重に情報を見極める必要があります。
まず、危険性という言葉が指している内容を整理することが大切です。
多くの場合、それは「情報漏洩のリスク」「製品の安全性」「サポート体制への不安」の3つに集約されます。
特に情報漏洩に関しては、中国メーカーという背景が過度に不安視される傾向があります。
しかし、実際には多くのグローバル企業と同様、LenovoもISO認証やセキュリティポリシーの強化に取り組んでおり、一概に危険と断定できるものではありません。
また、製品自体の安全性についても、基本的には国際基準に則った製造プロセスを経て市場に出ているため、構造的に「危ない」といえるレベルではありません。
とはいえ、初期不良やトラブルがゼロではないのも事実です。
これはどのメーカーにも共通する課題であり、Lenovoだけに限定されるものではありません。
さらに言えば、情報端末を使う上での危険性は、製品そのものよりも「ユーザーの使い方」によって大きく変わります。
例えば、セキュリティソフトを導入しないままインターネットに接続したり、不審なメールを開封したりすれば、どのメーカーのPCであってもリスクは高まります。
このように、Lenovo製品に特有の危険性が常にあるわけではなく、使い方や情報の受け取り方によって印象が左右されている部分が多いといえます。
過去の事例や世間の声に惑わされるのではなく、製品の仕様・用途・対策をしっかりと理解した上で判断することが求められます。
過去の不祥事とセキュリティ問題
Lenovoは過去にいくつかの不祥事やセキュリティ問題を起こしており、それが現在も「やめとけ」と言われる一因になっています。
もっとも有名なのは、2014年から2015年にかけて発覚した「Superfish(スーパーフィッシュ)」というアドウェア問題です。
このアドウェアは、一部のLenovo製PCにプリインストールされていたもので、ユーザーのWeb閲覧情報を収集し、広告を表示する仕組みを持っていました。
問題は、Superfishが暗号化された通信の内容まで監視できる設計になっており、第三者による盗聴や情報改ざんのリスクが指摘された点にあります。
この出来事は世界中のメディアで大きく報道され、Lenovoに対する信頼を大きく揺るがす結果となりました。
さらに、この事件を通じて注目されたのが、ユーザーが知らないうちにソフトウェアが仕込まれていたという事実です。
購入時点ですでに不要なプログラムが動いていたことに、多くの消費者が衝撃を受けました。
その後Lenovoは謝罪し、Superfishのプリインストールを中止。
セキュリティ強化への取り組みを表明しました。
他にも、一部の企業や政府機関で「Lenovo製品の使用を制限する」といった方針が取られた事例があります。
これは必ずしもLenovo製品に重大な欠陥があったからではなく、国際的な政治リスクやサイバーセキュリティ上の懸念に基づく判断が多いです。
つまり、技術的に「危険」とされたのではなく、情報管理の観点から「万が一」のリスクを避けるための措置といえるでしょう。
このように、過去の不祥事は実際に存在しましたが、その多くは既に是正され、再発防止策も講じられています。
ただし、消費者の記憶に残るインパクトは大きく、今でもLenovo製品に対する疑念の根拠になっているのが現実です。
レノボの評判は実際どうなのか

レノボの評判については、「良い」と「悪い」が大きく分かれる傾向があります。
それは製品のラインナップが幅広く、ユーザー層も多様であることに起因しています。
個々の目的に応じた製品選びができていれば満足度は高くなりますが、期待と異なる使い方をすると評価が一気に下がってしまうのです。
例えば、価格面で見るとレノボは非常に競争力があります。
特にエントリーモデルは同スペック帯の製品に比べて安価で、初めてパソコンを買う人や、コストを重視するユーザーから高評価を得ています。
ネット検索や動画視聴など、基本的な作業に使う分には問題なく、多くのレビューでも「コスパが良い」と紹介されています。
一方で、悪い評判の中には「品質にばらつきがある」「サポートがいまひとつ」といった指摘があります。
とくに低価格モデルにおいては、筐体の作りがチープに感じられたり、動作がもたついたりすることがあります。
サポートに関しても、「電話がつながりにくい」「日本語が通じづらい」といった声が一部ユーザーから報告されています。
また、法人向けのThinkPadシリーズや高性能モデルに関しては、評価が非常に高いのも特徴です。
耐久性やキーボードの打ち心地、冷却性能などにおいて高く評価されており、実際に企業や教育機関などで多く導入されています。
このような製品に触れたユーザーからは「信頼できる」「長く使える」といった好意的な意見が多く見られます。
つまり、レノボの評判は製品のカテゴリや使い方によって大きく異なります。
全体として見れば「安価なモデルはそれなりの品質」「高価格帯は高性能で安心」という傾向があるため、自分の目的と予算を明確にして選ぶことが、満足度を左右する重要なポイントになります。
レノボのサポート体制と国内生産事情
レノボ製品に対する評価の中で、とくに注目されるのがサポート体制の質と生産拠点の問題です。
価格帯や性能が優れていても、購入後のサポートが不十分であれば、トラブル時にストレスを感じるユーザーも多くなります。
また、どこで製品が作られているのかも、信頼性や品質を左右する要素として見られがちです。
まずサポート体制についてですが、レノボは日本国内に「レノボ・ジャパン合同会社」という法人を構えています。
これは、問い合わせや修理対応を含めたサービス窓口を国内に持つことを意味し、海外メーカーでありながら一定の安心感を提供しています。
サポート窓口には電話、チャット、Webフォームなどがあり、製品の種類によっては翌営業日オンサイト修理などのビジネス向けサービスも展開されています。
ただし、すべてのユーザーが満足しているわけではありません。
「電話がつながりにくい」「対応がマニュアル的」といった不満も一定数見られます。
特に個人ユーザー向けの低価格帯モデルでは、サポートの対応が限定的になる傾向があるため、手厚いサービスを求めるなら、上位機種や有償のサポートプランを検討することが必要です。
次に国内生産事情についてですが、レノボは実は日本国内にも生産拠点を持っています。
代表的なのは、山形県米沢市にある「NECパーソナルコンピュータ」の工場です。
これはNECとレノボの合弁会社であり、ThinkPadシリーズの一部やNECブランドのPCがここで製造されています。
つまり、中国製に不安を感じているユーザーであっても、日本国内で生産されているモデルを選べば、その懸念を和らげることが可能です。
このように、レノボのサポート体制や生産体制は「中国メーカー=不安」という単純な構図では語れません。
必要に応じてサポートの質を見極め、製造地にも注意を払うことで、より満足度の高い購入ができるはずです。
やめとけと騒がれる理由は都市伝説?
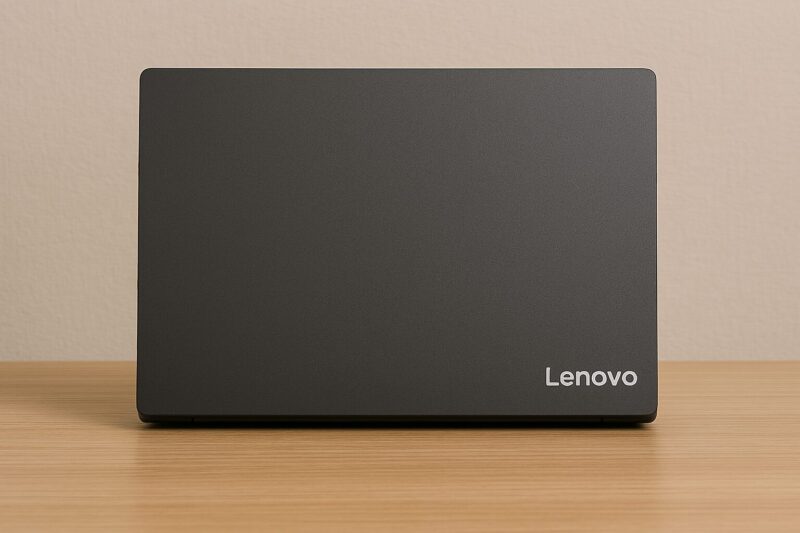
「レノボはやめとけ」といった声がネット上で広まる中、そのすべてが事実に基づいているわけではありません。
むしろ、多くの情報は噂や誤解、あるいは過去の事例が一人歩きしたものに過ぎないケースも見受けられます。
一つの要因として、かつてのSuperfish問題や、中国政府との関係性を不安視する声が挙げられます。
これらは確かに当時のレノボにとって信頼を揺るがすものでしたが、既に再発防止策が講じられており、現在の製品にはそのようなソフトウェアは含まれていません。
にもかかわらず、ネットの掲示板やSNSでは、こうした古い情報が今でも拡散されています。
さらに、口コミサイトやレビューの一部では、「買ってすぐ壊れた」「初期不良があった」などの書き込みが目立ちます。
しかし、これらはどのメーカーでも一定数発生する可能性があり、個別の体験が全体の品質を示しているとは限りません。
それにもかかわらず、特定のネガティブな意見だけが強調されることで、「レノボ=やめたほうがいい」というイメージが形成されてしまうのです。
こうした現象は、いわゆる「都市伝説」と似た構造を持っています。
真偽不明の話が繰り返し語られ、あたかも一般常識のように扱われてしまう。
これを鵜呑みにしてしまうと、本来得られるはずの選択肢を見誤ることになります。
このように考えると、「やめとけ」という言葉がどこまで信頼できる情報に基づいているのか、冷静に見極めることが大切です。
ネット上の声だけでなく、製品仕様や利用目的、最新のサポート体制なども含めて総合的に判断する姿勢が求められます。
レノボを選ぶべきユーザーの特徴とは
Lenovo製品は万人向けというより、ある特定のニーズを持つユーザーに向いている傾向があります。
そのため、使用目的や予算、サポートへの期待値などを明確にした上で選ぶことで、購入後の満足度が大きく変わってきます。
まず、コストパフォーマンスを重視する人には非常におすすめです。
Lenovoのエントリーモデルは、同等スペックの他社製品と比べても価格が抑えられており、インターネットや動画視聴、Officeソフトの使用といった軽めの作業には十分対応できます。
学生や初めてパソコンを購入する方にとっては、必要最低限をしっかりカバーしてくれる安心感があります。
次に、ビジネス用途で安定した操作性を求めるユーザーにも適しています。
特にThinkPadシリーズは、打鍵感の良さや堅牢な設計、セキュリティ機能の高さが評価されており、長時間の使用や持ち運びが多い仕事環境に適しています。
企業や教育機関での導入実績が多いことからも、その信頼性の高さがうかがえます。
また、カスタマイズ性を重視するユーザーにも向いています。
Lenovoの直販サイトでは、CPU・メモリ・ストレージ構成などを細かく選べるモデルが多く、用途に応じた最適な1台を選ぶことができます。
既製品では満足できない人にとっては、自由度の高さが大きなメリットになるでしょう。
反対に、「国内ブランドにこだわりたい」「サポートは日本語で丁寧に対応してほしい」といったニーズを持つ方には、あまり適していない可能性もあります。
サポート体制には一定の差があるため、不安を感じる場合は事前に問い合わせ方法や対応時間などを確認しておくことをおすすめします。
このように、Lenovoは価格と性能のバランスが取れた製品を多く揃えており、必要なポイントを見極めて選べば非常に満足度の高い選択肢となります。
どのようなユーザーに向いているのかを正しく理解することが、後悔しない購入につながります。

