MacBookのグラフィック性能を強化したいと考え、MacBookにグラボを外付けする方がいます。
外付けGPU(eGPU)を使えば映像編集や3D作業が快適になりますが、「やめとけ」と言われる理由も存在します。
特にM1チップ搭載のMacはeGPU非対応で、Thunderbolt以外の接続では使用できません。
iMacでも対応機種は限られており、ケース選びや設定も複雑です。
導入コストが高く、デメリットも多いため慎重な検討が必要です。
また、外付けSSDとHDDのどちらを選ぶかによっても利便性が変わります。
本記事では、eGPU導入で「何が変わるのか」を含め、基礎から具体例まで分かりやすく解説します。
Macでの活用を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
MacBookにグラボを外付けする基本と注意点
- 外付けGPUはM1に非対応なので注意
- 外付けGPUがやめとけと言われる理由
- 外付けGPUのデメリットとは何か
- Thunderbolt以外の接続は使える?
- 外付けグラボで何が変わるのかを解説
- iMacにグラボを外付けするにはどう使う?
外付けGPUはM1に非対応なので注意

Appleが2020年以降に導入したM1チップ搭載のMacでは、外付けGPU(eGPU)が利用できません。
これは技術的な制限であり、設定やドライバの工夫では解決できない根本的な非対応です。
M1チップはApple独自のアーキテクチャを採用しており、それまでのIntelベースのMacとはまったく異なる設計思想に基づいています。
そのため、従来のeGPUが前提としているThunderbolt経由でのGPU拡張に対応していません。
このように聞くと「Thunderbolt 3や4が付いているのに、どうして使えないのか」と疑問に思うかもしれません。
確かにハードウェア的には接続は可能ですが、M1チップには外部GPUを認識・活用するためのドライバやAPIが提供されていないため、macOS上でeGPUは機能しません。
Apple自身も公式に「M1シリーズではeGPUはサポート対象外」と明言しているため、将来的なアップデートでも使えるようになる見込みは今のところないとされています。
これから外付けGPUを導入しようと考えているMacユーザーは、自身のMacがIntelプロセッサ搭載モデルかM1チップ搭載モデルかを必ず確認しておく必要があります。
特に中古や型落ちのモデルを購入する場合、eGPUを目的とするならば「Intel製のMac」「macOS High Sierra 10.13.4以降」が大前提となる条件です。
eGPUを活用するためには、対応するMacと対応するmacOSバージョンがそろっていなければ意味がありません。
M1以降のMacユーザーは、内蔵GPUの性能を前提とした使い方をするか、最初から高性能GPUを搭載したWindows PCなどを選ぶ方が現実的です。
外付けGPUがやめとけと言われる理由
外付けGPU(eGPU)は、使い方次第でMacやノートPCのグラフィック性能を大きく向上させることが可能ですが、それでも「やめとけ」と言われる理由があります。
その一番の理由は、導入の難易度とコストに対して、得られるパフォーマンスのバランスが悪い点です。
まず、eGPUは接続しただけで即座に本来の性能を発揮するものではありません。
設定やドライバのインストール、macOSのバージョンとの適合確認など、かなりの手間が必要になります。
また、アプリ側がeGPUに対応していないケースも多く、思ったような効果が得られないこともあります。
さらに、eGPUの性能をフルに引き出すには、外付けディスプレイをeGPU側に直接接続しなければならないという制限も存在します。
もうひとつの課題は、コストです。
eGPU本体とは別に、対応するグラフィックカードと高出力な電源付きケースを用意しなければならず、合計で10万円を超えることも珍しくありません。
それに対して、同じ予算であればデスクトップ型のゲーミングPCや、GPU内蔵の高性能ノートPCが購入できるため、eGPUにこだわる意味が薄れる場合があります。
これに加えて、Mac環境では使用できるGPUの種類がAMD製に限られるなど、選択肢の幅も狭くなります。
さらに、前述の通り、Apple Silicon(M1以降)ではeGPUは完全に非対応です。
このような背景から、外付けGPUは「面倒」「高い」「効果が限定的」と見られ、「やめとけ」との意見が根強くあるのです。
ただし、対応環境と目的が明確な上級ユーザーにとっては、eGPUは非常に有効なツールであることも事実です。
慎重に判断することが重要です。
外付けGPUのデメリットとは何か
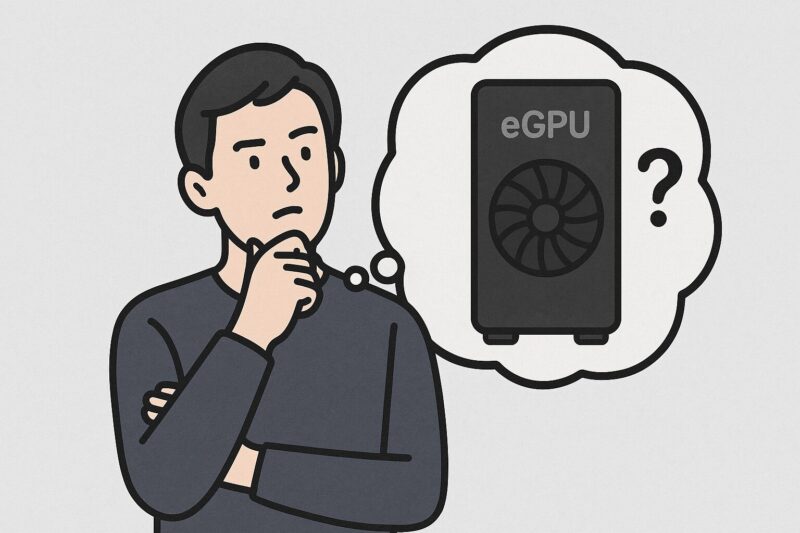
外付けGPU(eGPU)には多くの魅力がありますが、同時にいくつかの重要なデメリットが存在します。
特に初心者にとっては、このデメリットを事前に理解しておかないと、購入後に後悔するケースも少なくありません。
最も大きなデメリットは、パフォーマンスのロスです。
Thunderbolt 3や4といった高速インターフェースを使っていても、デスクトップPCの内部に直接接続されたGPUと比べると、約30〜40%、場合によっては50%以上の性能低下が発生すると言われています。
これは、Thunderbolt接続の帯域幅や、データ転送のタイムラグが原因です。
さらに、eGPUの運用には追加のスペースと電力が必要です。
専用の拡張ボックスは決して小さくはなく、設置スペースに余裕がない人にとっては大きな負担になります。
また、発熱量もそれなりにあるため、冷却対策や音対策も重要です。
特に静かな環境で作業したい場合は、ファン音がストレスになることもあります。
そして、互換性の問題も無視できません。
macOSでは、対応しているグラフィックカードが限定されており、使える製品はほとんどがAMD製です。
NVIDIA製GPUは公式にサポートされておらず、独自の設定や非公式ドライバを必要とする場合もあります。
これにより、購入時の選択肢が大きく制限されます。
さらに、アプリケーション側がeGPUを有効活用できる設計になっていない場合、グラフィック性能が上がっても処理速度にほとんど変化が見られないこともあります。
たとえば、内蔵ディスプレイ上でアプリを動かしていると、eGPUではなく内蔵GPUが使われてしまうこともあります。
このように、eGPUには一定の制約や技術的なハードルがつきまといます。
導入を検討する際は、利便性だけでなく、実際の用途や環境に合っているかどうかを冷静に見極めることが大切です。
Thunderbolt以外の接続は使える?
現状、Macで外付けGPU(eGPU)を使用する場合、Thunderbolt 3 または Thunderbolt 4 が事実上の必須条件です。
これは、macOSがeGPUとの接続に対応している唯一のポートがThunderboltであるためであり、USB-CやUSB 3.0といった他の一般的なインターフェースでは、eGPUの接続・認識はできません。
ここで「USB Type-Cの形状ならThunderboltと同じでは?」と混同してしまう方もいますが、注意が必要です。
見た目は似ていても、ThunderboltとUSB-Cは中身が全く異なる規格であり、データ転送速度や映像出力、電力供給の面で大きな違いがあります。
Thunderboltは高速なPCI Express通信をサポートしているため、GPUとのやりとりに必要な帯域を確保できるのです。
たとえば、Thunderbolt非対応のMacBookやiMacに、USB-Cポート経由で外付けGPUを接続しようとしても、macOSはそれをグラフィックプロセッサとして認識することはありません。
物理的にケーブルを挿すことはできても、ソフトウェア的に接続は成立しないため、機能しないのです。
なお、Windows環境ではUSB経由のドッキングステーションで疑似的に外付けGPUを使う方法も一部存在しますが、Macではそういった手段は基本的にサポートされていません。
また、macOS自体が他社製ドライバに制限を設けているため、無理やり動かすと不安定になる可能性もあります。
このように、MacでeGPUを使いたい場合は、「Thunderbolt対応」であることが絶対条件となります。
購入前には、お使いのMacにThunderboltポートが搭載されているかをしっかり確認しておきましょう。
外付けグラボで何が変わるのかを解説
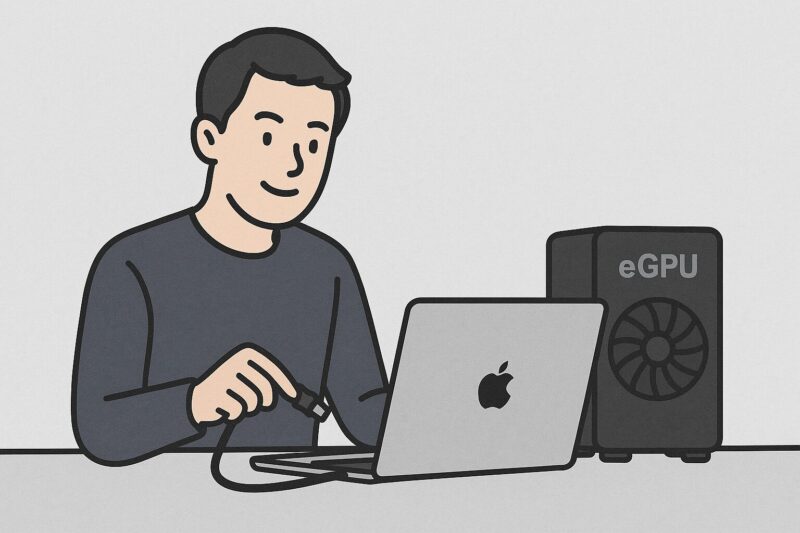
外付けグラフィックボード(eGPU)を導入することで、Macのグラフィックス性能は大幅に向上します。
特にノート型のMacBookや、iMacの下位モデルなど、内蔵GPUの処理能力が限られている環境では、eGPUがその弱点を補ってくれます。
まず変わるのは、描画処理の速度です。
動画編集、3Dモデリング、ゲーム、VRなどGPU負荷が高い作業では、内蔵GPUではカクつきや動作の遅延が起こることがあります。
しかし、eGPUを活用すれば、高解像度のレンダリングやリアルタイム処理もスムーズになります。
たとえば、4K動画のプレビューがスムーズに行える、3Dゲームが高フレームレートで動くといった変化を体感できます。
また、外部ディスプレイとの接続環境も改善します。
eGPUはDisplayPortやHDMI出力に対応しているため、複数台のモニターを高解像度で同時出力できるようになります。
MacBook単体では難しいデュアルディスプレイや4K/60Hz出力といった環境も構築可能です。
さらに、アプリによってはeGPUを利用することで内部のGPUリソースを節約でき、その結果、全体的なシステムパフォーマンスが向上することもあります。
Final Cut Proのように、プロ向けソフトがeGPUを優先的に使う設計になっていれば、その恩恵は非常に大きくなります。
ただし、すべてのアプリがeGPUに対応しているわけではない点には注意が必要です。
また、Thunderbolt接続という仕様上、内蔵GPUと比べて処理遅延や性能のロスが発生する場合もあります。
それでも、特定の作業においては「外付けグラボを導入しただけで作業効率が格段に向上する」という実感を得られるでしょう。
用途が明確であるなら、導入の価値は十分にあります。
iMacにグラボを外付けするにはどう使う?
iMacで外付けGPUを使うためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず前提として、Intelプロセッサを搭載しているiMacであることが大前提です。
Apple Silicon(M1以降)のiMacは、現時点で外付けGPUに対応していません。
対応機種であれば、macOS High Sierra 10.13.4以降がインストールされている必要があります。
その上で、Thunderbolt 3ポートを使って外付けGPUボックスを接続します。
グラフィックボードは、macOSが公式に対応を表明しているAMD製のモデルを選ぶ必要があります。
たとえば、Radeon RX 570、580、6800 XT などが一般的な対応モデルです。
接続後、macOSがeGPUを自動的に認識すれば、追加設定なしでも使用が開始されます。
ただし、アプリによってはeGPUを手動で指定する必要があります。
macOS Mojave以降では、アプリの「情報を見る」から「外部 GPU を優先」にチェックを入れることで、iMac本体のディスプレイでもeGPUの効果を得られるようになります。
また、外付けディスプレイをeGPUに直接接続すれば、より安定したパフォーマンスを引き出すことができます。
これは、アプリがどのGPUを使うかをディスプレイの出力先に応じて判断する仕組みがあるためです。
つまり、eGPUにディスプレイをつなぐことで、確実にeGPUが使われるようになります。
このとき注意すべきなのは、eGPUの接続・解除は必ず「メニューバーから安全に取り外し操作」を行うことです。
強制的に電源を切ってしまうと、macOSが不安定になる恐れがあります。
このように、iMacでも条件さえそろえば、外付けGPUを用いた高負荷処理が実現可能です。
作業の快適さやクリエイティブ環境の拡張を求めるユーザーにとっては、有効な選択肢となるでしょう。
MacBookにグラボを外付けするための選び方と使い方
- Macで外部GPUを優先するにはどうすればいい
- 外付けグラボにおすすめのケースとは
- Mac対応のGPUとケースの組み合わせ例
- MacBookの外付けSSDと外付けHDDどっちがいい
- GPU接続時にトラブルを防ぐ方法
- 外付けグラボ導入前に確認すべきポイント
Macで外部GPUを優先するにはどうすればいい

Macで外付けGPU(eGPU)を導入しても、必ずしもすべてのアプリが自動的にeGPUを使用するわけではありません。
macOSの仕様上、アプリケーションがどのGPUを使うかは条件によって異なるため、外部GPUを優先的に使いたい場合は、設定を明確にしておく必要があります。
macOS Mojave(10.14)以降では、特定のアプリに対して「外部GPUを優先する」オプションが用意されています。
手順は以下の通りです。
まず、Finderで対象のアプリを探し、そのアプリの本体(通常は「アプリケーション」フォルダ内)を「controlキーを押しながらクリック」し、「情報を見る(command + I)」を開きます。
すると、「外部GPUを優先」のチェックボックスが表示されるので、ここにチェックを入れるだけです。
この設定を行うことで、eGPUが接続されている状態であれば、macOSはそのアプリをeGPU経由で動作させるようになります。
これにより、映像処理や3Dレンダリングなど、高度なグラフィックス機能をeGPUに任せることができます。
また、外付けモニターをeGPUに直接つなぐことで、アプリケーションが自動的にeGPUを使用するようにする方法もあります。
この方法は特に、macOS High Sierra 10.13.4~Mojave初期のバージョンで有効とされており、外部ディスプレイを経由してアプリが描画される場合、eGPUを利用する設計になっているためです。
ただし、すべてのアプリがeGPUの切り替えに対応しているわけではありません。
たとえば、Final Cut Proのように独自にGPUを管理するアプリケーションでは、このチェックボックスは無視されるケースもあります。
また、eGPU非対応のアプリも存在するため、動作確認は事前に必要です。
このように、設定は簡単でも、対応アプリや接続方法に注意することが大切です。
環境に応じて最適な方法を選び、効果的にeGPUを活用しましょう。
外付けグラボにおすすめのケースとは
外付けグラフィックボード(eGPU)をMacで使うには、グラボ本体を収納する専用ケース(eGPUシャーシ)が必要です。
このケースは単なる外装ではなく、電源ユニットや冷却機構、Thunderbolt接続ポートなどを内蔵しており、性能と安定性を左右する重要なパーツです。
おすすめのeGPUケースを選ぶ際のポイントは大きく3つあります。
まず1つ目は電源供給能力です。
グラフィックボードは高負荷時に大量の電力を消費するため、十分な電力を供給できる電源(少なくとも350W〜650W)が内蔵されているケースを選ぶ必要があります。
特にMacBook Proなどノート型Macと接続する場合、ケースから本体への給電(充電)機能があるかも確認しておきましょう。
2つ目はThunderbolt 3または4への対応です。
MacではeGPUの接続にThunderboltが必須なので、これに対応したインターフェースがあるかどうかは最優先の確認ポイントです。
旧型のThunderbolt 2を使っている場合は変換アダプタが必要になりますが、パフォーマンスは低下しやすいため注意が必要です。
3つ目は対応サイズと拡張性です。
大型GPUを使う場合、ケース内のスペースや冷却設計が適切でなければ動作が不安定になることもあります。
大型のグラボを搭載する予定があるなら、「2.5スロット対応」「フルレングス対応」などの記載があるモデルを選ぶと安心です。
具体的な製品としては、以下のようなケースがMac向けに高評価を得ています。
- Sonnet eGFX Breakaway Boxシリーズ(350W~650W)
- Razer Core X / Core X Chroma
- OWC Mercury Helios FX
これらは給電能力、冷却性能、対応GPUの幅広さなどの点でバランスが良く、Macとの相性も良好です。
また、Thunderboltケーブルが付属しているモデルもあり、別途用意する必要がない点も初心者にはありがたい仕様です。
このように、eGPUケースは「グラフィックボードを入れる箱」以上の役割を持ちます。
安定したパフォーマンスを引き出すには、ケース選びも妥協せず、自分のGPUやMac環境に合ったものを慎重に選ぶことが大切です。
Mac対応のGPUとケースの組み合わせ例
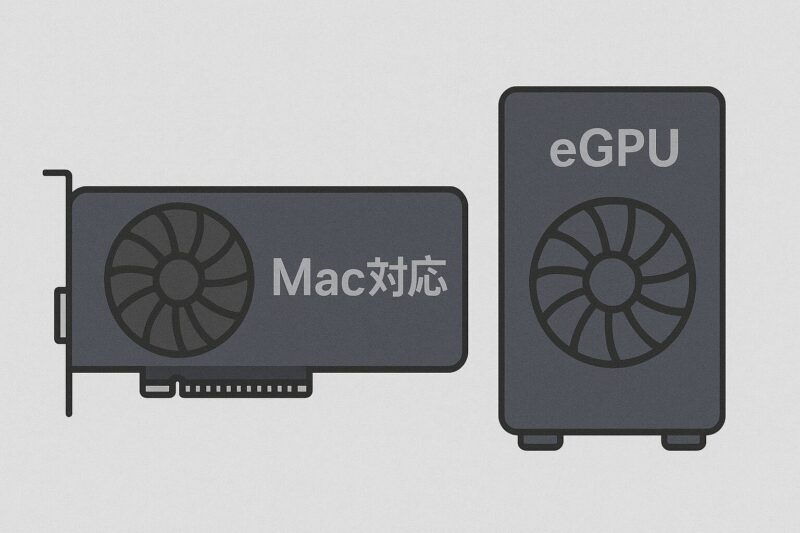
Macで外付けGPU(eGPU)を使うには、macOSが正式に対応しているグラフィックカードを選ぶ必要があります。
特にAMD製GPUが前提となっており、NVIDIA製は公式にサポートされていない点に注意が必要です。
さらに、使用するGPUによって、最適なケース(eGPUシャーシ)も変わってきます。
ここでは、具体的な組み合わせ例をご紹介します。
たとえば、Radeon RX 580は、比較的安価で安定性が高く、macOS High Sierra 10.13.4以降に対応しています。
このGPUは多くのプロフェッショナルにも使用されており、動画編集や3D処理にも十分対応可能です。
組み合わせるケースとしては、Sonnet eGFX Breakaway Box 350Wが定番です。
電力や冷却に関して十分なスペックを備えており、コストパフォーマンスにも優れています。
より高性能を求めるなら、Radeon RX 6800 XTやRadeon RX 6900 XTといったRDNA2世代のGPUも選択肢に入ります。
これらはmacOS Big Sur 11.4以降で使用可能です。
これらを使う場合は、電力消費が高いため、Sonnet eGFX Breakaway Box 650WやRazer Core Xのように高出力対応のケースが必要です。
また、持ち運びや省スペースを重視したい場合は、GPU内蔵型のコンパクトeGPU製品も検討できます。
たとえば、Blackmagic eGPUやSonnet Radeon RX 570 Breakaway Puckは、グラボがあらかじめ組み込まれており、Thunderboltケーブルで接続するだけですぐに使用できます。
互換性の心配も少ないため、初心者でも扱いやすいのが魅力です。
このように、MacでeGPUを活用するには、GPUとケースの相性が非常に重要です。
公式の推奨リストやmacOSのバージョンとの適合も確認しながら、必要な性能と予算に合わせて最適な組み合わせを選ぶことが成功の鍵になります。
導入前には各パーツの仕様やレビューをしっかり確認し、自分の用途に合った構成を整えるようにしましょう。
MacBookの外付けSSDと外付けHDDどっちがいい
MacBookに外部ストレージを追加する際、外付けSSDと外付けHDDのどちらを選ぶべきか悩む方は多いです。
それぞれに特徴があるため、自分の利用目的に合った選択が求められます。
スピードを重視するのであれば、外付けSSDがおすすめです。
SSDは読み書き速度が非常に速く、macOSの起動ディスクとして使うことも可能です。
アプリの起動やファイルのコピーもストレスなく行えるため、動画編集や高解像度写真の管理など、処理負荷の高い作業に適しています。
さらに、衝撃に強く、動作音がほぼないのも特徴です。
一方で、コストパフォーマンスを重視するなら外付けHDDが有力です。
大容量のストレージが比較的安価で手に入るため、バックアップ用や長期保管のデータ保存には向いています。
ただし、物理的な回転ディスクを使用しているため衝撃には弱く、アクセス速度もSSDより劣ります。
頻繁に出し入れする用途にはあまり適しません。
例えば、macOSのTime Machineバックアップ専用にするならHDDで十分です。
しかし、動画ファイルを編集しながら直接読み書きしたい場合や、システムの拡張ストレージとして使いたい場合にはSSDのほうが快適です。
このように、どちらが良いかは「何を保存したいか」「どのように使いたいか」によって異なります。
スピード・携帯性・静音性を重視するならSSD、容量と価格を重視するならHDD。
目的に応じた選択が、MacBookのパフォーマンスをより引き出すカギとなります。
GPU接続時にトラブルを防ぐ方法

外付けGPU(eGPU)をMacに接続するとき、適切に手順を踏まなければ認識されなかったり、システムがフリーズするなどのトラブルが起こることがあります。
しかし、いくつかの注意点を守るだけで、多くの問題は未然に防ぐことが可能です。
まず最初に重要なのは、接続のタイミングと手順です。
Macが起動中にeGPUを接続する場合は、ユーザーがログインした後にThunderboltケーブルを差し込むようにしましょう。
ログイン前に接続すると、eGPUが正しく認識されないケースが報告されています。
また、macOSでは「eGPUの安全な取り外し」が可能ですので、外すときはメニューバーから正しく操作することが大切です。
次に、使用するケーブルとポートの品質も確認しましょう。
必ずThunderbolt 3または4に対応した純正または高品質なケーブルを使用してください。
MacBook Proの一部モデルでは、Thunderboltポートの左右で性能が異なることもあるため、なるべく左側のポートに接続するのが無難です。
さらに、macOSのバージョンやドライバの対応状況を確認することも欠かせません。
macOSのアップデート直後はeGPUとの互換性に問題が生じる場合があるため、導入前にそのバージョンでの動作実績をチェックしておくと安心です。
特にAMD製の特定GPUしかサポートしていないため、サポート対象外の製品を使おうとしても正常に機能しません。
加えて、アプリケーションの設定も見直すべき点です。
eGPUを使いたいアプリに対して「外部GPUを優先」を設定しておかないと、内蔵GPUのままで処理されることがあります。
アプリを終了したうえで、Finderから「情報を見る」パネルを開き、外部GPUを優先する設定を行っておきましょう。
これらのポイントを踏まえることで、eGPU接続にまつわるトラブルは大きく軽減されます。
万一、問題が発生しても、落ち着いて接続を見直し、公式サポートやレビュー情報を参考にして原因を特定する姿勢が大切です。
外付けグラボ導入前に確認すべきポイント
外付けグラフィックボード(eGPU)をMacで使おうと考えているなら、導入前にいくつかの確認事項があります。
これらを事前にチェックしておかないと、機器の購入後に「動かない」「思っていた性能が出ない」といったトラブルに直面する可能性があります。
まず確認すべきは、お使いのMacのプロセッサとポートの種類です。
Apple Silicon(M1、M2シリーズなど)を搭載したMacはeGPUに対応していません。
外付けGPUが使えるのは、Intelプロセッサを搭載し、かつThunderbolt 3以上のポートを持つMacのみです。
この条件を満たしていないと、ハードウェアを揃えても認識すらされません。
次に、macOSのバージョンも確認が必要です。
macOS High Sierra 10.13.4以降からeGPUに対応していますが、macOSのアップデートによって動作が不安定になるケースもあるため、導入予定のGPUが現在のmacOSバージョンで確実に動作するか、公式サポートページなどで確認しましょう。
また、使用したいアプリがeGPUに対応しているかどうかも非常に重要です。
全てのアプリがeGPUの性能を活用できるわけではなく、例えばPhotoshopやFinal Cut Proのような一部のプロ向けアプリでしか恩恵を受けられない場合もあります。
必要な作業とアプリケーションの相性を把握しておくことで、無駄な投資を防げます。
さらに、eGPUケースとGPUの互換性も忘れてはなりません。
GPUが大型であれば、ケースのサイズや電力供給能力が不足することがあります。
ケースが対応しているグラフィックボードの種類や最大電力を事前にチェックし、組み合わせに無理がないようにすることが大切です。
最後に、接続時の発熱や騒音への理解も求められます。
eGPUは処理中に高温になり、ファンの動作音も発生します。
静音環境で作業したい方や、限られたスペースで使う方は、静音設計の製品や冷却性能の高いケースを選ぶと良いでしょう。
このように、導入前にしっかりと情報を整理し、対応機種や環境を確認することで、トラブルを未然に防ぎ、eGPUのパフォーマンスを最大限に引き出すことができます。
初めての導入であれば、互換性のある一体型eGPU製品から始めるのも一つの選択肢です。

